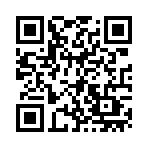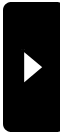2021/10/31
半生菓子…よく年配の方が好むようなお菓子のイメージがあります。が、実はどらやきとか大福とかマシュマロとか…若い方も実は好きな方が多いんじゃないかなぁと思っています。
そんな半生菓子の宝庫が下伊那です。
なぜだかわかりませんが、下伊那には半生菓子を製造する企業が集まっています。
スーパーには各社の半生菓子コーナーができているほど。
今日は半生菓子を仕入れに豊丘村にあるとよおかマルシェへ。
施設内にあるスーパーでお気に入りのお菓子を仕入れます。
天恵製菓「力士餅」

最中菓子が大好きな僕がドハマリしているお菓子です。
力士の名の通り、中には餅が入っていて食感もGooodです。
そして、このとよおかマルシェには、天恵製菓のアウトレット商品もあるのでお気に入りのお菓子があればうんとラッキーなんです。
(本日はハロウィーン関係のお菓子だったからカスタードとかチョコレートだったので…残念でした)
半生菓子好きの皆様、下伊那にでかけた際にはぜひスーパー、そしてとよおかマルシェにお立ち寄りください。

そんな半生菓子の宝庫が下伊那です。
なぜだかわかりませんが、下伊那には半生菓子を製造する企業が集まっています。
スーパーには各社の半生菓子コーナーができているほど。
今日は半生菓子を仕入れに豊丘村にあるとよおかマルシェへ。
施設内にあるスーパーでお気に入りのお菓子を仕入れます。
天恵製菓「力士餅」
最中菓子が大好きな僕がドハマリしているお菓子です。
力士の名の通り、中には餅が入っていて食感もGooodです。
そして、このとよおかマルシェには、天恵製菓のアウトレット商品もあるのでお気に入りのお菓子があればうんとラッキーなんです。
(本日はハロウィーン関係のお菓子だったからカスタードとかチョコレートだったので…残念でした)
半生菓子好きの皆様、下伊那にでかけた際にはぜひスーパー、そしてとよおかマルシェにお立ち寄りください。
2021/10/30
人って何かやろう!と思い立って行動したら、その行動に対しての成果を感じたいと誰もが思うはずです。
そして、成果を感じることができなければ継続はほぼ無理だと思います。
先日から始まった第3期利益の組立図を作るゼミナールは利益の組立図を作るだけではなく「実践」し「検証」するまでのサイクルを実際に体感してもらいます。
組立図を作る⇒そのとおりに実践する⇒検証する⇒組立図を修正(作る)…
最終的にはこの循環を回し続けられるようになることを望んでいます。
ここで重要なのが「検証」です。
僕もそうですがこの「検証」を意識せず、結果的に循環せず終わってしまう場合が多いと感じています。
図)ひとしごとの循環図(米澤晋也さん)

その理由の1つに「検証するための情報が決められていないため感覚だけの検証になってしまっている」と感じます。これは僕の反省点でもあり、今回のゼミで再認識したことでもあります。
例えば飲食店が有料広告を出したとします。
来てほしいお客さま層がたくさん読んでいるであろう地元フリーペーパーに掲載します。
結果、思った以上の結果が出なかった…
多分ですが「地元フリーペーパーって効果ない」と他責として納得し循環は止まってしまいます。
一方「有料広告で問い合わせが5人来る」とこの行動に対しての目標を立てていたらどうでしょうか?
まず「有料広告からの問い合わせなのか、それ以外の問い合わせなのか」を検証する何かを用意します。
これは食べログも仕込んでいる検証方法で食べログ経由の電話(050から始まる番号)だと「食べログからの電話です」という案内があったあとに、通話が始まります。
これで「食べログ広告の効果」を実感させているわけです。
このように目標を設定し、設定した目標を調べられるように用意しておく。
循環を実現するために「検証するための情報」が非常に重要であることがわかります。
そしてもう一つ。
検証をするので「検証しやすい数値化できる何かを目標にする」ことも重要です。
そうすることで検証がしやすくなります。
これは僕にとっての戒めの言葉ですが、いろいろな計画って作って満足、それを実践することが「目標」になりがちです。
そうならないよう「検証」にも計画と同じくらい重要視し循環が回っていくようにしていきましょう。
…はい、僕自身へ向かっての内容でしたとさ。
■こちらの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです
そして、成果を感じることができなければ継続はほぼ無理だと思います。
先日から始まった第3期利益の組立図を作るゼミナールは利益の組立図を作るだけではなく「実践」し「検証」するまでのサイクルを実際に体感してもらいます。
組立図を作る⇒そのとおりに実践する⇒検証する⇒組立図を修正(作る)…
最終的にはこの循環を回し続けられるようになることを望んでいます。
ここで重要なのが「検証」です。
僕もそうですがこの「検証」を意識せず、結果的に循環せず終わってしまう場合が多いと感じています。
図)ひとしごとの循環図(米澤晋也さん)

その理由の1つに「検証するための情報が決められていないため感覚だけの検証になってしまっている」と感じます。これは僕の反省点でもあり、今回のゼミで再認識したことでもあります。
例えば飲食店が有料広告を出したとします。
来てほしいお客さま層がたくさん読んでいるであろう地元フリーペーパーに掲載します。
結果、思った以上の結果が出なかった…
多分ですが「地元フリーペーパーって効果ない」と他責として納得し循環は止まってしまいます。
一方「有料広告で問い合わせが5人来る」とこの行動に対しての目標を立てていたらどうでしょうか?
まず「有料広告からの問い合わせなのか、それ以外の問い合わせなのか」を検証する何かを用意します。
これは食べログも仕込んでいる検証方法で食べログ経由の電話(050から始まる番号)だと「食べログからの電話です」という案内があったあとに、通話が始まります。
これで「食べログ広告の効果」を実感させているわけです。
このように目標を設定し、設定した目標を調べられるように用意しておく。
循環を実現するために「検証するための情報」が非常に重要であることがわかります。
そしてもう一つ。
検証をするので「検証しやすい数値化できる何かを目標にする」ことも重要です。
そうすることで検証がしやすくなります。
これは僕にとっての戒めの言葉ですが、いろいろな計画って作って満足、それを実践することが「目標」になりがちです。
そうならないよう「検証」にも計画と同じくらい重要視し循環が回っていくようにしていきましょう。
…はい、僕自身へ向かっての内容でしたとさ。
■こちらの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです
2021/10/28
僕がココ数年一番チカラを入れている支援の1つがこの「利益の組立図を作るゼミナール」です。3年目となる本年度も沢山の方に応援していただき昨日開講しました。3回目となる今年は、過去2回の振り返りからその伝え方も大きく変更、始まり前はうんと不安でしたが1日目が終わってみれば今までで一番わかり易い構成だった…
タグ :商工会議所
2021/10/29
令和3年度税制改正で帳簿書類を電子的に保存する事がうんと厳しくなりました。
それは「電子取引のデータをプリントアウトした書面の保存が認められなくなる」
ということです。
具体例だと、Amazonやカウネットで買った消耗品の領収書は電子データでの保存が義務化され、印刷した紙で保存できなくなります。

※Impress Watch 「施行目前「改正電子帳簿保存法」ってなに? 3つ+αのポイント」より
※わかりやすくまとまっています。
ただ、保存ならいいんですが…厄介なのは「真実性の確保」「可視性の確保」が求められていることです。
真実性の確保とは「ファイルがいつ受け渡しされたものかがわかり、後で変更されたりしていない」ことを担保しなければいならないこと。
可視性の確保とは「ファイルを開けは読める内容になっていて、日付や取引先などですぐ検索できる」ことを実現しなければいけないこと。
この2つって、多分パソコンのフォルダに保存しただけではできません。
これだけ聞くと「えっ、それって大企業だけで中小・小規模企業は関係ないんぢゃないの?」と思ってしまいますが、残念なことに大中小関係なく全部の企業や事業者に適応となります。
どうするんだろう…
僕も研究してシンプルかつ安価にできる方法がありましたら改めて発信します。
当面は「請求書は紙で受取る(郵送もしくはファクスしてむらう)」という対応になりそうです。
なんだかなー
それは「電子取引のデータをプリントアウトした書面の保存が認められなくなる」
ということです。
具体例だと、Amazonやカウネットで買った消耗品の領収書は電子データでの保存が義務化され、印刷した紙で保存できなくなります。

※Impress Watch 「施行目前「改正電子帳簿保存法」ってなに? 3つ+αのポイント」より
※わかりやすくまとまっています。
ただ、保存ならいいんですが…厄介なのは「真実性の確保」「可視性の確保」が求められていることです。
真実性の確保とは「ファイルがいつ受け渡しされたものかがわかり、後で変更されたりしていない」ことを担保しなければいならないこと。
可視性の確保とは「ファイルを開けは読める内容になっていて、日付や取引先などですぐ検索できる」ことを実現しなければいけないこと。
この2つって、多分パソコンのフォルダに保存しただけではできません。
これだけ聞くと「えっ、それって大企業だけで中小・小規模企業は関係ないんぢゃないの?」と思ってしまいますが、残念なことに大中小関係なく全部の企業や事業者に適応となります。
どうするんだろう…
僕も研究してシンプルかつ安価にできる方法がありましたら改めて発信します。
当面は「請求書は紙で受取る(郵送もしくはファクスしてむらう)」という対応になりそうです。
なんだかなー
タグ :商工会議所
2021/10/28
僕がココ数年一番チカラを入れている支援の1つがこの「利益の組立図を作るゼミナール」です。3年目となる本年度も沢山の方に応援していただき昨日開講しました。
3回目となる今年は、過去2回の振り返りからその伝え方も大きく変更、始まり前はうんと不安でしたが1日目が終わってみれば今までで一番わかり易い構成だったと確信しています。
毎回「わかりやすく、実践しやすく」するためメンテナンスをしてくれるコーチのヨネちゃん、緑さん、本当にありがとうございます。
そんなゼミで、僕が気がついたコトを各回ごと抜粋してお伝えしていきたいと思います。
利益の組立図とは『事業計画』のことです。
補助金の影響なのか事業計画というとうんと難しいイメージがあります。
でも本当はシンプルです。
『モノが売れるという現象=人が行動した結果』
え~!何いまさら言ってるの…と思う方がほとんどだと思います。
でも、この行動の設計こそが「事業計画」だと確信しています。
◯◯分析のようなものは、この設計でちゃんと組立ができるのか=成功率を確認するための情報にすぎません。

事業計画は「お客さまの行動を設計する」と言い換えて間違えありません。
そのように定義すると、利益の組立図は「お客さまの行動を軸に、お店や企業が行う行動を考えていく」ことになることがわかります。

ここで視点を確実なものにする重要なことがあります。
商売は利益があってのものです。
だから当然「売上が欲しい」「売上のために」という考えが軸になってしまいます。
そうすると「売上のために◯◯をしなくては」という考えしか浮かんで来なくなります。
そうするとどうなるのか…
今、企業でやっていない何かを考え始めます。
例えば飲食店だと割引サービスとかスタンプカード割引とか◯◯フェアになります。
一方お客さまの行動を軸にすると、現在企業がやっていることそのものを拡大してくことになるのであえて新しいことに挑戦する必要がありません。
労力やお金の面から見てもお客さまの行動を軸にするほうが中小、小規模企業には向いていると思います。
図)目的=軸が売上にあるとこうなる(オフィス緑 中塚緑さん)

図)お客さまを軸にした考え(オフィス緑 中塚緑さん)


第1日目の1つの気づきでした。
もう一つの気づき「循環を回して小さいな成功体験を得る」は明日以降のお伝えします。

■こちらの記事も合わせてお読みいただけたら嬉しいです
3回目となる今年は、過去2回の振り返りからその伝え方も大きく変更、始まり前はうんと不安でしたが1日目が終わってみれば今までで一番わかり易い構成だったと確信しています。
毎回「わかりやすく、実践しやすく」するためメンテナンスをしてくれるコーチのヨネちゃん、緑さん、本当にありがとうございます。
そんなゼミで、僕が気がついたコトを各回ごと抜粋してお伝えしていきたいと思います。
利益の組立図とは『事業計画』のことです。
補助金の影響なのか事業計画というとうんと難しいイメージがあります。
でも本当はシンプルです。
『モノが売れるという現象=人が行動した結果』
え~!何いまさら言ってるの…と思う方がほとんどだと思います。
でも、この行動の設計こそが「事業計画」だと確信しています。
◯◯分析のようなものは、この設計でちゃんと組立ができるのか=成功率を確認するための情報にすぎません。

事業計画は「お客さまの行動を設計する」と言い換えて間違えありません。
そのように定義すると、利益の組立図は「お客さまの行動を軸に、お店や企業が行う行動を考えていく」ことになることがわかります。

ここで視点を確実なものにする重要なことがあります。
商売は利益があってのものです。
だから当然「売上が欲しい」「売上のために」という考えが軸になってしまいます。
そうすると「売上のために◯◯をしなくては」という考えしか浮かんで来なくなります。
そうするとどうなるのか…
今、企業でやっていない何かを考え始めます。
例えば飲食店だと割引サービスとかスタンプカード割引とか◯◯フェアになります。
一方お客さまの行動を軸にすると、現在企業がやっていることそのものを拡大してくことになるのであえて新しいことに挑戦する必要がありません。
労力やお金の面から見てもお客さまの行動を軸にするほうが中小、小規模企業には向いていると思います。
図)目的=軸が売上にあるとこうなる(オフィス緑 中塚緑さん)

図)お客さまを軸にした考え(オフィス緑 中塚緑さん)


第1日目の1つの気づきでした。
もう一つの気づき「循環を回して小さいな成功体験を得る」は明日以降のお伝えします。

■こちらの記事も合わせてお読みいただけたら嬉しいです
2021/10/14
商工会議所のスタッフになってたくさんの経営者の方や、これから経営者になる方々とお逢いすることができました。そしてサラリーマン時代には全然ピンとこなかった企業の「理念」「らしさ」「ミッション」「ビジョン」「バリュー」等々の意味や大切さもこのコロナ禍でようやくなんとなく分かるようになってきた気がし…
タグ :商工会議所
2021/10/27
今日は一年で一番大事な仕事との一つがスタートした日。
第1回目が終わって振返りの会をしてます。

第1回目が終わって振返りの会をしてます。

2021/10/26
3年間無利子、低金利で話題になった日本生活金融公庫(以下「国金」と書きます)がで新型コロナ特別貸付は全国的に利用する事業者さんがかなりいらっしゃるそう。
僕の働く長野県諏訪市でも多くの事業者さんがご利用していて、今もなお相談や利用が多いそうです。
この制度が始まって1年以上が経過することもあり、利用したコトを知っている事業者さんへ現在の状況を聞きに行く事もなるべく実施しています。
その中で地味に多い「手続きを忘れている」ことがあります。
それが「3年分の利子補給の申込みをしていない」ことです。
3年間無利子のからくりは『3年間分の利息を先に現金としてお渡しする』仕組みです。
つまり、利息を3年分補助するからその補助金の中から支払ってくださいという「先払い金」のような仕組みです。
そして「補助金」なので、事業者さんが申請しないと補助金は振り込まれません。
これを忘れている事業者さんが地味に多くいらっしゃいます。
多分ですが、市町村や都道府県が行っている利子補給は何も手続きがなくても支払った利息金額が振り込まれるし、そもそも無利子と行っているので「申請を必要とする補助金」というイメージも無いと思います。
しかも、融資決定後2週間から1ヶ月後に改めて申請の案内が送られてくるので見落としてしまう方も多いようです。
ちなみに書類は日本生活金融公庫の封筒で届きます。(支店によっては「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度のご案内」と封筒に印刷されている場合もあるようですが、ない場合も多いため後回しにしてしまう方もいらっしゃるようです)

その封筒の中には「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度のご案内」と「申請書」が入っています。

これを「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局」に送らなければいけません。
しかも、申請には期限があって、現在は2022年11月30日で、期限内に申請がない場合は利子補給が受けられなくなります。
国金のコロナ対策有志をご利用頂いた皆様で「あれ?申請していないや…」と気づかれた方は申請をお忘れなくお願いします。
僕の働く長野県諏訪市でも多くの事業者さんがご利用していて、今もなお相談や利用が多いそうです。
この制度が始まって1年以上が経過することもあり、利用したコトを知っている事業者さんへ現在の状況を聞きに行く事もなるべく実施しています。
その中で地味に多い「手続きを忘れている」ことがあります。
それが「3年分の利子補給の申込みをしていない」ことです。
3年間無利子のからくりは『3年間分の利息を先に現金としてお渡しする』仕組みです。
つまり、利息を3年分補助するからその補助金の中から支払ってくださいという「先払い金」のような仕組みです。
そして「補助金」なので、事業者さんが申請しないと補助金は振り込まれません。
これを忘れている事業者さんが地味に多くいらっしゃいます。
多分ですが、市町村や都道府県が行っている利子補給は何も手続きがなくても支払った利息金額が振り込まれるし、そもそも無利子と行っているので「申請を必要とする補助金」というイメージも無いと思います。
しかも、融資決定後2週間から1ヶ月後に改めて申請の案内が送られてくるので見落としてしまう方も多いようです。
ちなみに書類は日本生活金融公庫の封筒で届きます。(支店によっては「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度のご案内」と封筒に印刷されている場合もあるようですが、ない場合も多いため後回しにしてしまう方もいらっしゃるようです)
その封筒の中には「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度のご案内」と「申請書」が入っています。
これを「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局」に送らなければいけません。
しかも、申請には期限があって、現在は2022年11月30日で、期限内に申請がない場合は利子補給が受けられなくなります。
国金のコロナ対策有志をご利用頂いた皆様で「あれ?申請していないや…」と気づかれた方は申請をお忘れなくお願いします。
タグ :商工会議所
2021/10/25
何度も何度もあっていたり連絡をもらっていたりするといざというときにその人の顔が浮かんでくることがありませんか?
あと、なんだか親近感が湧いて話しやすかったりする経験ってないでしょうか?
逆に、本当にご無沙汰になると、いざというときにその人の顔が浮かんでこなかったり、浮かんできても話しかけづらかったりした経験がないでしょうか?
僕自身、このような経験は幾度とあって…というか、かなりあるような気がします。
長野県大町市に「おおまぴょん」という市のキャラクターがいます。
いわゆる市町村の「ゆるきゃら」ですが、このおおまぴょんの露出度が非常に高いんです。
市役所も商工会議所もいろいろな団体が使っているから街の至るところに登場していて大町市でおおまぴょんを見ないことはないと思います。
というか「あそこにも、ここにも…このキャラどれだけいるの?」と多くの人は思うぐらいです。





このくらいアチラコチラで目にすると、当然知名度もあがるし、愛着度も上がります。
ちなみに、前職でお世話になった50~60歳以上のおっさんに聞いても「おおまぴょん」の名前はわかりませんが、その存在ははっきりと認識しています。中には「おおまぴょんはなー」なんて教えてくれるおっさんも。
◯◯を知ってもらう、愛着を持ってもらうために接触する頻度を上げる。
これって、商売や当然商工会議所でも同じことだと思いませんか?
例えば新型コロナで外食を控えていたお客さまが、制限解除後に行くお店を選択するとき、きっと新型コロナ禍でも接触頻度が高かったお店が選択肢に上がってくるような気がします。「制限解除になったからリアルに逢いに行きたいね」みたいな感じだと。
こんな事例もDesignNAP Drフジコさん(藤戸さん)教えてもらったことがあります。
和歌山市にはお土産やお使い物のトップに君臨する「紀州銘菓 かげろう」というお菓子があるそうです。
各お菓子屋さんは「かげろうに追いつけ追いこせ」みたいな目標になっているぐらいだそう。
その商品は街の至るところに看板が出ていて、このお菓子を知らない人でも気になっちゃうんぐらいの接触頻度だそう。
実際に気になって購入といった販売の組み立てだそうです。
こんな話から、もしかしたら「接触頻度の高さ=売上高」という考えもできるかもしれません。
ぢゃ、どうやって接触頻度を上げていくのか…
それは、お近くの商工会議所、商工会のスタッフさんに聞いてみてください。きっと助けてくれると思います。
あと、なんだか親近感が湧いて話しやすかったりする経験ってないでしょうか?
逆に、本当にご無沙汰になると、いざというときにその人の顔が浮かんでこなかったり、浮かんできても話しかけづらかったりした経験がないでしょうか?
僕自身、このような経験は幾度とあって…というか、かなりあるような気がします。
長野県大町市に「おおまぴょん」という市のキャラクターがいます。
いわゆる市町村の「ゆるきゃら」ですが、このおおまぴょんの露出度が非常に高いんです。
市役所も商工会議所もいろいろな団体が使っているから街の至るところに登場していて大町市でおおまぴょんを見ないことはないと思います。
というか「あそこにも、ここにも…このキャラどれだけいるの?」と多くの人は思うぐらいです。
このくらいアチラコチラで目にすると、当然知名度もあがるし、愛着度も上がります。
ちなみに、前職でお世話になった50~60歳以上のおっさんに聞いても「おおまぴょん」の名前はわかりませんが、その存在ははっきりと認識しています。中には「おおまぴょんはなー」なんて教えてくれるおっさんも。
◯◯を知ってもらう、愛着を持ってもらうために接触する頻度を上げる。
これって、商売や当然商工会議所でも同じことだと思いませんか?
例えば新型コロナで外食を控えていたお客さまが、制限解除後に行くお店を選択するとき、きっと新型コロナ禍でも接触頻度が高かったお店が選択肢に上がってくるような気がします。「制限解除になったからリアルに逢いに行きたいね」みたいな感じだと。
こんな事例もDesignNAP Drフジコさん(藤戸さん)教えてもらったことがあります。
和歌山市にはお土産やお使い物のトップに君臨する「紀州銘菓 かげろう」というお菓子があるそうです。
各お菓子屋さんは「かげろうに追いつけ追いこせ」みたいな目標になっているぐらいだそう。
その商品は街の至るところに看板が出ていて、このお菓子を知らない人でも気になっちゃうんぐらいの接触頻度だそう。
実際に気になって購入といった販売の組み立てだそうです。
こんな話から、もしかしたら「接触頻度の高さ=売上高」という考えもできるかもしれません。
ぢゃ、どうやって接触頻度を上げていくのか…
それは、お近くの商工会議所、商工会のスタッフさんに聞いてみてください。きっと助けてくれると思います。
タグ :商工会議所
2021/10/24
新型コロナ感染症の影響でたくさんの方が集まるイベントが中止になっています。
特に密集するマラソン大会はほとんど開催されていません。
そして、僕が働く諏訪市も7000人以上のランナーが走る「諏訪湖マラソン大会」がありますが、2年間開催がされていません。
僕は走ることが嫌いですが、お客さまに誘われてここ数年連続出場→いつもギリギリ完走を果たしています。
大会数ヶ月前になると「完走しなきゃ」と走り始め大会が終わるとまたは知らなくなります。
でも「完走する」という目的に向かって頑張れるのっていいなぁと。
来年は3年ぶりの開催を期待していますが、人気のある大会なので申し込めるかなぁ…その前に完走できるように日々努力していきます。2年分おっさんになっていますからね。

特に密集するマラソン大会はほとんど開催されていません。
そして、僕が働く諏訪市も7000人以上のランナーが走る「諏訪湖マラソン大会」がありますが、2年間開催がされていません。
僕は走ることが嫌いですが、お客さまに誘われてここ数年連続出場→いつもギリギリ完走を果たしています。
大会数ヶ月前になると「完走しなきゃ」と走り始め大会が終わるとまたは知らなくなります。
でも「完走する」という目的に向かって頑張れるのっていいなぁと。
来年は3年ぶりの開催を期待していますが、人気のある大会なので申し込めるかなぁ…その前に完走できるように日々努力していきます。2年分おっさんになっていますからね。

2021/10/23
B級グルメ…最近聞かなくなったなぁ…と感じている僕です。
B級グルメブームは「ご当地グルメでまちおこしの祭典!B-1グランプリ」が開催されるようになって加速したと思っています。
よく見ると「まちおこしの祭典」…そう、まちおこしといえば商工会議所、商工会が大活躍される分野です。
といっても、商工会議所を知らない方にはピンッと来ないかもしれません。
全国各地の商工会議所、商工会が街おこしのためB級グルメを作ったり、全国に広めたりした事業をやっていました。
僕も仕事でB級グルメ的な仕事に幾度となく関わってきましたが、ほとんどが「あれ?いまどうしている?」状態で「事業自体がなかったこと」になっています。
多分ですが、全国の商工会議所、商工会等があの時期に一生懸命に行った同じような事業の多くは同じ状態ではないか?と思っています。(大変失礼ですが…)
その一方、今もなお根強く地域に根ざした料理として続いているものもあります。
その違いはなんなんでしょうか?
僕はこう思っています。
『地域の食文化として根付いたか、根付かなかったか』です。
つまり、商工会議所等が行ってきた事業は「新しい食文化を作る」、そしてその文化が地域の新しい魅力になって街がより豊かになるということだったんだと思っています。
ちなみに「文化」はとは…
「文化」は民族や社会の風習・伝統・思考方法・価値観などの総称で、世代を通じて伝承されていくものを意味する。
その地域に暮らす人達の生活に当たり前のように入り込んでいる。
もしくは、その地域の産業として多くの事業者が関わっている。
文化って具体的にこんな状態だと思っています。
そう考えると「新たに食文化を作る」って、すごく大変なことだと思うんです。
販売してくれる事業者さんをコツコツと増やし、住民や旅行者にコツコツと知ってもらって食べてもらう。
そして、できれば住民の生活に入り込み、何度も何度も購入してくれて、そしていろいろな方に「美味しいよ」とか「諏訪といったら◯◯ね」って教えるようになる。
こんな状態になる前に、何らかの原因でほ多くが途絶えちゃって、結局「食文化」にはならなかったんだろうなと。
◯◯の文化を新しく作る。こんな難しいことに商工会議所や商工会は取組んでいることを知っていただけたら嬉しいです。
…余談ですが、「今、すでにある食文化を多くの方に知ってもらう」のほうが労力も少なくて済むし、成功率も高いことが解っていただけると思います。独特の食文化がある地域って羨ましいです(T_T)

B級グルメブームは「ご当地グルメでまちおこしの祭典!B-1グランプリ」が開催されるようになって加速したと思っています。
よく見ると「まちおこしの祭典」…そう、まちおこしといえば商工会議所、商工会が大活躍される分野です。
といっても、商工会議所を知らない方にはピンッと来ないかもしれません。
全国各地の商工会議所、商工会が街おこしのためB級グルメを作ったり、全国に広めたりした事業をやっていました。
僕も仕事でB級グルメ的な仕事に幾度となく関わってきましたが、ほとんどが「あれ?いまどうしている?」状態で「事業自体がなかったこと」になっています。
多分ですが、全国の商工会議所、商工会等があの時期に一生懸命に行った同じような事業の多くは同じ状態ではないか?と思っています。(大変失礼ですが…)
その一方、今もなお根強く地域に根ざした料理として続いているものもあります。
その違いはなんなんでしょうか?
僕はこう思っています。
『地域の食文化として根付いたか、根付かなかったか』です。
つまり、商工会議所等が行ってきた事業は「新しい食文化を作る」、そしてその文化が地域の新しい魅力になって街がより豊かになるということだったんだと思っています。
ちなみに「文化」はとは…
「文化」は民族や社会の風習・伝統・思考方法・価値観などの総称で、世代を通じて伝承されていくものを意味する。
その地域に暮らす人達の生活に当たり前のように入り込んでいる。
もしくは、その地域の産業として多くの事業者が関わっている。
文化って具体的にこんな状態だと思っています。
そう考えると「新たに食文化を作る」って、すごく大変なことだと思うんです。
販売してくれる事業者さんをコツコツと増やし、住民や旅行者にコツコツと知ってもらって食べてもらう。
そして、できれば住民の生活に入り込み、何度も何度も購入してくれて、そしていろいろな方に「美味しいよ」とか「諏訪といったら◯◯ね」って教えるようになる。
こんな状態になる前に、何らかの原因でほ多くが途絶えちゃって、結局「食文化」にはならなかったんだろうなと。
◯◯の文化を新しく作る。こんな難しいことに商工会議所や商工会は取組んでいることを知っていただけたら嬉しいです。
…余談ですが、「今、すでにある食文化を多くの方に知ってもらう」のほうが労力も少なくて済むし、成功率も高いことが解っていただけると思います。独特の食文化がある地域って羨ましいです(T_T)

タグ :商工会議所
2021/10/22
政府が進める「生産性向上」とか人手不足とかに対応するため、コンビニのセミセルフレジ立ったり、セルフレジだったり、無人販売だったりと今までは定員さん=人が対応してくれたことが人を介さない商売になってきているとふと気が付きました。
例えば僕の生活でもそうです。
コンビニでは定員さんがバーコードを読み込んでくれますが、支払方法を自分で選び、領収書も自分で受け取ります。
ガソリンスタンドもそうです。自分で入れて自分で精算します。
インターネットでの買い物もそうです。もちろん定員さんがいるわけもないので、ポチッとタッチすれば商品が玄関先に届けられます。最近は宅急便やさんも「置配」があるから顔を合わせないこともあったりします。
コンビニのコーヒーもそうです。
僕はあまり飲みませんが、自分でボタンを押してコーヒーを入れます。スタッフさんが煎れてくれていたローソンでさえ現在はボタンポチッと方式に変わりました。

生産性向上が進むと「ひとけ:人気」がなくなってくる…そんな寂しさを感じています。
商品を買うときにひとけがなくなるとどうなるのか、僕は「そのお店に対する感謝の気持ち」とか「信頼関係」とかが薄れていくような気がしています。
自動販売機でジュースを買うときに、自動販売機に向かって「ありがとう、今日も1日頑張れるよ!」なんて声に出して言う人ってほどんど居ないと思います。
生産性向上って一番費用が高価な「人の労力を削減する」ことばかりに目が行ってしまうとちょっと怖いなーって、素人ながらに感じます。
現在、飲食店オーナーから一番多い相談が「セルフオーダーシステムの導入」です。
お客さまのスマホから注文できるというアレです。(QRコードを読み取ってというやつ)
導入費用も抑えられるため皆さん興味があります。
僕は導入に大賛成です。
なぜかと言うとホールスタッフさんの時間に余裕が出るからです。
今まで各テーブルに呼ばれて注文を伺っていた時間が削減できるからです。
その削減した時間で何をするのか?
それが事業者さんにとって大切な判断になると思います。
時間が削減できたから2人で接客していたホールスタッフを1人に削減する。
コレも生産性向上です。
逆に、空いた時間で接客の質を上げることで注文数や来店頻度が増えたのも生産性向上です。
セミセルフレジを導入したコンビニにも当てはまると思います。
レジスタッフさんが行っていた仕事をお客さまが行うわけなのでスタッフさんの仕事量は減ります。
でも、お客さまの目の前には立っています。
仕事量が減ってできた余裕をどのように使うのか?
レジが喋ってくれるから、ただ黙って立っているのか?
それとも、接客の質を上げる何かをするのか?
人の労力を「一番高価な経費」と捉えるのか?
それともお店や企業の「メンバー」として捉えるのか?
…書きながらとっちらかってしまいましたが「人気のない商売」ってちょっと怖いな…と思う今日このごろなのでした。
例えば僕の生活でもそうです。
コンビニでは定員さんがバーコードを読み込んでくれますが、支払方法を自分で選び、領収書も自分で受け取ります。
ガソリンスタンドもそうです。自分で入れて自分で精算します。
インターネットでの買い物もそうです。もちろん定員さんがいるわけもないので、ポチッとタッチすれば商品が玄関先に届けられます。最近は宅急便やさんも「置配」があるから顔を合わせないこともあったりします。
コンビニのコーヒーもそうです。
僕はあまり飲みませんが、自分でボタンを押してコーヒーを入れます。スタッフさんが煎れてくれていたローソンでさえ現在はボタンポチッと方式に変わりました。

生産性向上が進むと「ひとけ:人気」がなくなってくる…そんな寂しさを感じています。
商品を買うときにひとけがなくなるとどうなるのか、僕は「そのお店に対する感謝の気持ち」とか「信頼関係」とかが薄れていくような気がしています。
自動販売機でジュースを買うときに、自動販売機に向かって「ありがとう、今日も1日頑張れるよ!」なんて声に出して言う人ってほどんど居ないと思います。
生産性向上って一番費用が高価な「人の労力を削減する」ことばかりに目が行ってしまうとちょっと怖いなーって、素人ながらに感じます。
現在、飲食店オーナーから一番多い相談が「セルフオーダーシステムの導入」です。
お客さまのスマホから注文できるというアレです。(QRコードを読み取ってというやつ)
導入費用も抑えられるため皆さん興味があります。
僕は導入に大賛成です。
なぜかと言うとホールスタッフさんの時間に余裕が出るからです。
今まで各テーブルに呼ばれて注文を伺っていた時間が削減できるからです。
その削減した時間で何をするのか?
それが事業者さんにとって大切な判断になると思います。
時間が削減できたから2人で接客していたホールスタッフを1人に削減する。
コレも生産性向上です。
逆に、空いた時間で接客の質を上げることで注文数や来店頻度が増えたのも生産性向上です。
セミセルフレジを導入したコンビニにも当てはまると思います。
レジスタッフさんが行っていた仕事をお客さまが行うわけなのでスタッフさんの仕事量は減ります。
でも、お客さまの目の前には立っています。
仕事量が減ってできた余裕をどのように使うのか?
レジが喋ってくれるから、ただ黙って立っているのか?
それとも、接客の質を上げる何かをするのか?
人の労力を「一番高価な経費」と捉えるのか?
それともお店や企業の「メンバー」として捉えるのか?
…書きながらとっちらかってしまいましたが「人気のない商売」ってちょっと怖いな…と思う今日このごろなのでした。
タグ :商工会議所