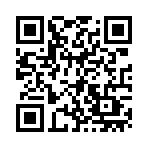ホームページがあれば売り上げは上がるのか?
2021/04/30
小規模事業者持続化補助金で最も利用が多いのが「ホームページを作る」「リニューアルする」です。
そして、それを導入する計画を拝見すると「新しい商品やサービスを売るために導入する」となっています。
小規模事業者持続化補助金の場合、政府(審査員)から求められている補助事業がそのような理由しか無いからかもしれませんが…
ホームページがあれば売上が上がる
そんな成果を期待した計画になります。
お恥ずかしながら僕には「ホームページ」を導入した売上や顧客数アップの知識がありません。
そのため、毎回分かったような顔をした自分がいました。
そこで、ホームページをどのように使っていくのか?
色々と調べて整理してみました。
とその前に、お世話になっている緑さん(オフィス緑 中塚緑さん)のブログのほうが解りやすいかも
https://ameblo.jp/midoma66/entry-12670099387.html
うんと大きく分けるとホームページは2つの使い方がある
ホームページは直接的な売上(一次的な売上げ)と、間接的な売上(二次的な売上)に利用できると思います。
1)直接的な売上や顧客アップを見込んでいる方の場合
お店や企業の存在すら知らない完全な新規顧客に対し利用するパターンになると思います。
ただ、この場合ホームページを持っているだけでは次につながらないことがわかります。
せっかくホームーページにたどり着いて御社や御社の商品やサービスに興味が湧いても、御社と実際に出会う方法である「動線」を引いてあげる必要があります。
動線を引いてあげないと「完全な新規顧客」さんはめんどくさいからいいや…
と、その時点で行動の完成が途切れてしまうからです。
では「動線」とは何か?
動線とは、興味を持ったお客さまがスムーズに次のアクションに移れるための何かです。
次の行動にエスコートするこんなイメージだと思います
例えば、電話番号がわかりやすく書いてあったり、商品が購入できるECサイトへの入口が見やすいところに配置されていたりするのがそうかなと思います。
2)間接的な売上を見込んでいる方の場合
何らかの方法でお店や企業を知った人、知っている人向け
例えば、すでにリアルで出逢っていて名刺にURLが書かれているとか、雑誌の記事やメディアでの登場で知っているとか、ポスティングしたチラシを見たとか…
その場合は「信頼を深める」とか「信頼をアップさせる」とかそんな目的で使う場合があると思います。
多分ですが、今の人は人一倍失敗したくないから、新しく行くお店や新規取引の企業等々ほぼ100%どんなんだ?ってことでインターネットで御社のことを調べると思います。
ホームページがないとさすがに...っていう時代なのかもしれませんが、必ず何かがヒットしてくると思います。
検索したのにヒットしなかったら…、それを不安に思いそれっきりになってしまうかもしれません。
逆に、ヒットしてそこでお客さまにとって思いのかけない情報があって「信頼を深める」ようになるなんてコトもあると思います。
ホームページがあることで、そういった間接的な打撃を軽減させる効果や信頼を深める効果が在ると思います。
これが「間接的な売上」だと思うんです。
ただし、やっぱりお客さまに焦点をあわせないとそうはならないとうな気がする…
ホームページって多分老若男女、全ての方がわかりやすい内容になっている場合が多いような気がします。
コンサルティングの先生や商工会議所の職員がよく教えてくれる「ターゲットを絞る(僕は焦点をあわせるが好みです)」ことを余りやらないような気がします。
多分ですが、小規模事業者にとって大切なのは「2)間接的な売上を見込んでいる」のような気がします。
ただし、発信するないようにグッときて興味を持っていただけるような「お客さまに焦点をあわせる=伝えたいお客さまをより具体的にする」ことが大切だと思います。
あくまで、僕の主観なので「こんなこと言っている人もいるんだな…」程度でご理解ください。

そして、それを導入する計画を拝見すると「新しい商品やサービスを売るために導入する」となっています。
小規模事業者持続化補助金の場合、政府(審査員)から求められている補助事業がそのような理由しか無いからかもしれませんが…
ホームページがあれば売上が上がる
そんな成果を期待した計画になります。
お恥ずかしながら僕には「ホームページ」を導入した売上や顧客数アップの知識がありません。
そのため、毎回分かったような顔をした自分がいました。
そこで、ホームページをどのように使っていくのか?
色々と調べて整理してみました。
とその前に、お世話になっている緑さん(オフィス緑 中塚緑さん)のブログのほうが解りやすいかも
https://ameblo.jp/midoma66/entry-12670099387.html
うんと大きく分けるとホームページは2つの使い方がある
ホームページは直接的な売上(一次的な売上げ)と、間接的な売上(二次的な売上)に利用できると思います。
1)直接的な売上や顧客アップを見込んでいる方の場合
お店や企業の存在すら知らない完全な新規顧客に対し利用するパターンになると思います。
ただ、この場合ホームページを持っているだけでは次につながらないことがわかります。
せっかくホームーページにたどり着いて御社や御社の商品やサービスに興味が湧いても、御社と実際に出会う方法である「動線」を引いてあげる必要があります。
動線を引いてあげないと「完全な新規顧客」さんはめんどくさいからいいや…
と、その時点で行動の完成が途切れてしまうからです。
では「動線」とは何か?
動線とは、興味を持ったお客さまがスムーズに次のアクションに移れるための何かです。
次の行動にエスコートするこんなイメージだと思います
例えば、電話番号がわかりやすく書いてあったり、商品が購入できるECサイトへの入口が見やすいところに配置されていたりするのがそうかなと思います。
2)間接的な売上を見込んでいる方の場合
何らかの方法でお店や企業を知った人、知っている人向け
例えば、すでにリアルで出逢っていて名刺にURLが書かれているとか、雑誌の記事やメディアでの登場で知っているとか、ポスティングしたチラシを見たとか…
その場合は「信頼を深める」とか「信頼をアップさせる」とかそんな目的で使う場合があると思います。
多分ですが、今の人は人一倍失敗したくないから、新しく行くお店や新規取引の企業等々ほぼ100%どんなんだ?ってことでインターネットで御社のことを調べると思います。
ホームページがないとさすがに...っていう時代なのかもしれませんが、必ず何かがヒットしてくると思います。
検索したのにヒットしなかったら…、それを不安に思いそれっきりになってしまうかもしれません。
逆に、ヒットしてそこでお客さまにとって思いのかけない情報があって「信頼を深める」ようになるなんてコトもあると思います。
ホームページがあることで、そういった間接的な打撃を軽減させる効果や信頼を深める効果が在ると思います。
これが「間接的な売上」だと思うんです。
ただし、やっぱりお客さまに焦点をあわせないとそうはならないとうな気がする…
ホームページって多分老若男女、全ての方がわかりやすい内容になっている場合が多いような気がします。
コンサルティングの先生や商工会議所の職員がよく教えてくれる「ターゲットを絞る(僕は焦点をあわせるが好みです)」ことを余りやらないような気がします。
多分ですが、小規模事業者にとって大切なのは「2)間接的な売上を見込んでいる」のような気がします。
ただし、発信するないようにグッときて興味を持っていただけるような「お客さまに焦点をあわせる=伝えたいお客さまをより具体的にする」ことが大切だと思います。
あくまで、僕の主観なので「こんなこと言っている人もいるんだな…」程度でご理解ください。