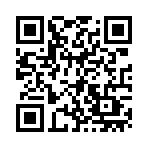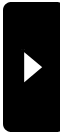2022/02/08
事業復活支援金と確定申告の相談、そして商工会議所自体の補助金申請で盆と正月が一度に来ている今日このごろです。
事業復活支援金で最近地味に多い質問が「2021年(R3)の確定申告は済ませなきゃいけないのか?」です。
答えば「場合によっては必要」です。
その場合「選択する基準期間が2021年11月~3月」のいずれかになる場合です。

◎事業復活支援金の詳細について P17
そしてもう一つ申請者に多い多い「えー!!」が「確定申告書と決算書がこんなにいるのー」です。
申請相談に見える事業者さんに多いのが「基準期間の書類しか持ってこない」です。
上記のように、指定された年の書類がすべて必要になるのでご注意ください。
始まったばかりなので混乱しますが、一つ一つ整理していけばそれほど難しい申請ではありません。
ご不明な点はお近くの商工会議所、商工会にお尋ねください。
事業復活支援金で最近地味に多い質問が「2021年(R3)の確定申告は済ませなきゃいけないのか?」です。
答えば「場合によっては必要」です。
その場合「選択する基準期間が2021年11月~3月」のいずれかになる場合です。

◎事業復活支援金の詳細について P17
そしてもう一つ申請者に多い多い「えー!!」が「確定申告書と決算書がこんなにいるのー」です。
申請相談に見える事業者さんに多いのが「基準期間の書類しか持ってこない」です。
上記のように、指定された年の書類がすべて必要になるのでご注意ください。
始まったばかりなので混乱しますが、一つ一つ整理していけばそれほど難しい申請ではありません。
ご不明な点はお近くの商工会議所、商工会にお尋ねください。
タグ :商工会議所
2022/01/27
本日から事前確認が始まった事業復活支援金。
そして、僕の働く長野県では本日から2月20日までまん延防止による飲食店の時短営業が始まりました。
時短営業には協力金が支払われます。
その協力金が事業復活支援金では「その月の売上」として計算されるので注意が必要です。

※事業復活支援金の詳細 P25
具体的には…長野県を例にあげます。
お酒を販売し21時までの営業を選択したお店の協力金は1日25,000円です。
時短営業養成期間は1月27日から2月20日までとなります。
各月の協力金は下記になります。
【各月の協力金額】
1月は5日間 X 25,000円 = 125,000円
2月は20日間 X 25,000円 = 500,000円
それぞれの協力金が、それぞれの月の売上に足された金額で比較することとなります。
例えば、1月の売上が50万、2月の売上が40万だった場合、
【比較に使う売上額】
1月の売上500,000円+協力金125,000円= 625,000円
2月の売上400,000円+協力金500,000円=900,000円
このことを飲食店の皆様にお伝えすると、ほとんどの方が理解していません。
該当しそうな方、ご注意をお願いします。
ちなみに、持続化給付金 、家賃支援給付金 、一時支援金 、月次支援金 、等の補助金は含まれないし、協力金も入金された月に事業収入として計上されていたら「その額は除いた額」になります。
ということで、事業復活支援金における協力金の扱いは下記のようになります。
【上記具体例から】
◯1月から2月の協力金が3月に支払われ、3月の事業収入に計上した。
→1月、2月の売上は協力金を加算。
→3月の事業収入はその額を除く。

※事業復活支援金の詳細 P24
そして、僕の働く長野県では本日から2月20日までまん延防止による飲食店の時短営業が始まりました。
時短営業には協力金が支払われます。
その協力金が事業復活支援金では「その月の売上」として計算されるので注意が必要です。

※事業復活支援金の詳細 P25
具体的には…長野県を例にあげます。
お酒を販売し21時までの営業を選択したお店の協力金は1日25,000円です。
時短営業養成期間は1月27日から2月20日までとなります。
各月の協力金は下記になります。
【各月の協力金額】
1月は5日間 X 25,000円 = 125,000円
2月は20日間 X 25,000円 = 500,000円
それぞれの協力金が、それぞれの月の売上に足された金額で比較することとなります。
例えば、1月の売上が50万、2月の売上が40万だった場合、
【比較に使う売上額】
1月の売上500,000円+協力金125,000円= 625,000円
2月の売上400,000円+協力金500,000円=900,000円
このことを飲食店の皆様にお伝えすると、ほとんどの方が理解していません。
該当しそうな方、ご注意をお願いします。
ちなみに、持続化給付金 、家賃支援給付金 、一時支援金 、月次支援金 、等の補助金は含まれないし、協力金も入金された月に事業収入として計上されていたら「その額は除いた額」になります。
ということで、事業復活支援金における協力金の扱いは下記のようになります。
【上記具体例から】
◯1月から2月の協力金が3月に支払われ、3月の事業収入に計上した。
→1月、2月の売上は協力金を加算。
→3月の事業収入はその額を除く。

※事業復活支援金の詳細 P24
タグ :商工会議所
2022/01/24
個人事業主最高50万円、法人最高250万円の運転資金を補助する「事業復活支援金」の申請が1月31日15時以降と発表されました。
この補助金で1番勘違いが一番多いのが昨年の「一時給付金、月次給付金」の対象だった「緊急事態宣言による移動制限により売上が減少した」ではなく
「新型コロナ感染症の影響を受けて売上が減少した」事業者さんが対象となります。

もう一つ今までとは異なるのが「30%以上~50%未満の減少」も追加されたことです。

この2点に注意が必要です。
給付対象は下記になります。
・新型コロナ感染症の影響を受けた事業者
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年、2019年、2020年の同じ月どおしを比較して30%以上減少した事業者
一時給付金、月次給付金を受給された方は、そのときのID、パスワードを使って申請すれば事前確認の必要はありません。(忘れたり、紛失した場合は事前確認の必要があります)

ざっくりとした説明ですが、一時給付金、月次給付金を受給されていない事業者さんもたくさん対象となると思います。
ご不明な点等々は、お近くの商工会議所、商工会、顧問税理士、メーン金融機関にご相談ください。

この補助金で1番勘違いが一番多いのが昨年の「一時給付金、月次給付金」の対象だった「緊急事態宣言による移動制限により売上が減少した」ではなく
「新型コロナ感染症の影響を受けて売上が減少した」事業者さんが対象となります。

もう一つ今までとは異なるのが「30%以上~50%未満の減少」も追加されたことです。

この2点に注意が必要です。
給付対象は下記になります。
・新型コロナ感染症の影響を受けた事業者
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年、2019年、2020年の同じ月どおしを比較して30%以上減少した事業者
一時給付金、月次給付金を受給された方は、そのときのID、パスワードを使って申請すれば事前確認の必要はありません。(忘れたり、紛失した場合は事前確認の必要があります)

ざっくりとした説明ですが、一時給付金、月次給付金を受給されていない事業者さんもたくさん対象となると思います。
ご不明な点等々は、お近くの商工会議所、商工会、顧問税理士、メーン金融機関にご相談ください。

タグ :商工会議所
数日前から長野県よりBCP(事業継続計画)の整備推進についての問い合わせがチョコチョコと入っていました。
「何なんだろうなー」程度にしか思っていまいせんでしたが、今朝の読売新聞の記事を見て「これかー!」と納得しました。
読売新聞の記事から…
政府が19日に改定した新型コロナ対策の基本的対処方針で、都道府県が、社会経済活動に不可欠な事業者に対し、欠勤者が多く発生した場合でも業務を継続するよう要請することが盛り込まれたそう。
要請された事業者はBCP(事業継続計画)に基づいて対応する方針だそう。
そういうことね…と。

※読売新聞より
BCPは数年前から政府が推し進めていますが僕の働く諏訪地域でもそれほど多くの事業者さんは整備していません。
というのも「テロや災害、システム障害や不祥事といった危機的状況下に置かれた場合でも重要な業務を継続するため」と説明があり、多くの事業者さんは「大企業のことでしょ…うちにはあまり関係ないし」と感じているからのように思えます。(あくまで僕の考えです。失礼をスイマセン)
ただ、今回の政府方針でその見方がかなり変わりました。
今回政府は「国民の日常生活を守るために事業継続を実現してほしい」「そのためにBCP計画に基づいた対応をしてほしい」と業務を継続する理由を明確にしています。
事業=多くの商売は地域や住民、そこで働くスタッフさん等々たくさんの方々の暮らしを助けたり、豊かにしているはずです。
特に『日常の生活を維持するための事業』、例えば食べ物、電気、ガス、燃料、水道はいまや生活には書かせません。病院もそうだし、交通もそうです。
その事業者さんの事業が止まってしまったら…
そんな基本的なことに気が付きました。
BCPは事業を継続することが目的ではなく、たくさんの人々の生活を守るコト、その事業者さんがサービスや商品を販売することができなくなることで困る人々をなくすこと。
そう言い換えることができます。
ちなみに、イオン(僕は未だにジャスコと言ってしまいますが…)はスタッフさんが出勤できなくて店舗営業が困難な場合、生活に欠かせない食料品売り場の営業(維持)を最優先させる行動をするそう。
本来ならBCPを整備してください!と商工会議所の立場では言わなければいけないかもしれませんが、整備できなかったとしてもご自身の商売が長い間休むことになったり、無くなってしまうことになった場合に、どんな商品、サービスにどのくらいの人が困るのか?
そんなコトを整理してみると直ぐに対応できる何かが見つかるかもしれません。
「何なんだろうなー」程度にしか思っていまいせんでしたが、今朝の読売新聞の記事を見て「これかー!」と納得しました。
読売新聞の記事から…
政府が19日に改定した新型コロナ対策の基本的対処方針で、都道府県が、社会経済活動に不可欠な事業者に対し、欠勤者が多く発生した場合でも業務を継続するよう要請することが盛り込まれたそう。
要請された事業者はBCP(事業継続計画)に基づいて対応する方針だそう。
そういうことね…と。

※読売新聞より
BCPは数年前から政府が推し進めていますが僕の働く諏訪地域でもそれほど多くの事業者さんは整備していません。
というのも「テロや災害、システム障害や不祥事といった危機的状況下に置かれた場合でも重要な業務を継続するため」と説明があり、多くの事業者さんは「大企業のことでしょ…うちにはあまり関係ないし」と感じているからのように思えます。(あくまで僕の考えです。失礼をスイマセン)
ただ、今回の政府方針でその見方がかなり変わりました。
今回政府は「国民の日常生活を守るために事業継続を実現してほしい」「そのためにBCP計画に基づいた対応をしてほしい」と業務を継続する理由を明確にしています。
事業=多くの商売は地域や住民、そこで働くスタッフさん等々たくさんの方々の暮らしを助けたり、豊かにしているはずです。
特に『日常の生活を維持するための事業』、例えば食べ物、電気、ガス、燃料、水道はいまや生活には書かせません。病院もそうだし、交通もそうです。
その事業者さんの事業が止まってしまったら…
そんな基本的なことに気が付きました。
BCPは事業を継続することが目的ではなく、たくさんの人々の生活を守るコト、その事業者さんがサービスや商品を販売することができなくなることで困る人々をなくすこと。
そう言い換えることができます。
ちなみに、イオン(僕は未だにジャスコと言ってしまいますが…)はスタッフさんが出勤できなくて店舗営業が困難な場合、生活に欠かせない食料品売り場の営業(維持)を最優先させる行動をするそう。
本来ならBCPを整備してください!と商工会議所の立場では言わなければいけないかもしれませんが、整備できなかったとしてもご自身の商売が長い間休むことになったり、無くなってしまうことになった場合に、どんな商品、サービスにどのくらいの人が困るのか?
そんなコトを整理してみると直ぐに対応できる何かが見つかるかもしれません。
タグ :商工会議所
2022/01/18
日本政策金融公庫(僕の中では国金、一般的には公庫?)で普通貸付を利用すると「団体信用生命保険」なるものに加入するかいなかを問われます。
そして「どうしよう、よくわからないし…」と相談する事業者さんが結構いらっしゃいます。
僕の考えはこの保険は任意だし、ご自身が仮に不慮な事故や病気で返済途中に亡くなった後も加入している保険や資産で返済をカバーできれば必要ないとお伝えしています。
有志を受ける側なので「入っとかなきゃまずいかな…」という気分になります全く影響はありません。
ではこの「団体信用生命保険とは何か?」をご説明します。
この保険は借主が死亡したり、高度障害状態になることによって借入金の返済ができなくなった場合に、残債を全て肩代わりしてくれる(残債がゼロになる)生命保険です。

京都銀行より借用 https://www.kyotobank.co.jp/kojin/loan/jyutaku/kiso/danshin.html
融資が決定した後の契約書等の入った封筒に加入の有無を確認する書類が同封されています。
加入は任意なので入る入らないは事由ですが、約50%の方が加入をされています。
上記にも説明したように、加入の判断材料はもしものときにご家族に迷惑がかかるか否かです。
例えば残金1,000万円の借金を残された方や介護される方が支払っていくわけです。
もちろん、他の生命保険等々で1,000万円を返済できれば全く問題ありません。
まずは「もしものとき、ご家族に明確がかかるかどうか」で考えていただけたら嬉しいです。
生命保険なので保険料がかかります。
この保険では「特約料」と言っていますが、保険料のことです。
元本を元に金額が決まり、完済するまで支払払います。
例えば1,000万円を7年で返済する場合、保険料総額は97,000円になります。

保険料は下記からシミュレーションできますの参考にしてください。
「特約料お支払額シミュレーション」
https://www.dansin.or.jp/insurance/business/simulation.php
この保険に入るか入らないかは自由だし、入らなかったからといって今後の融資が不利になることもありません。
自分の加入している他の保険の内容や迷惑をかけるかもしれない家族の状況、リスクに対する特約料の金額など、色々と考慮した上で、加入するかしないかを決断して下さい。
そして「どうしよう、よくわからないし…」と相談する事業者さんが結構いらっしゃいます。
僕の考えはこの保険は任意だし、ご自身が仮に不慮な事故や病気で返済途中に亡くなった後も加入している保険や資産で返済をカバーできれば必要ないとお伝えしています。
有志を受ける側なので「入っとかなきゃまずいかな…」という気分になります全く影響はありません。
ではこの「団体信用生命保険とは何か?」をご説明します。
この保険は借主が死亡したり、高度障害状態になることによって借入金の返済ができなくなった場合に、残債を全て肩代わりしてくれる(残債がゼロになる)生命保険です。

京都銀行より借用 https://www.kyotobank.co.jp/kojin/loan/jyutaku/kiso/danshin.html
融資が決定した後の契約書等の入った封筒に加入の有無を確認する書類が同封されています。
加入は任意なので入る入らないは事由ですが、約50%の方が加入をされています。
上記にも説明したように、加入の判断材料はもしものときにご家族に迷惑がかかるか否かです。
例えば残金1,000万円の借金を残された方や介護される方が支払っていくわけです。
もちろん、他の生命保険等々で1,000万円を返済できれば全く問題ありません。
まずは「もしものとき、ご家族に明確がかかるかどうか」で考えていただけたら嬉しいです。
生命保険なので保険料がかかります。
この保険では「特約料」と言っていますが、保険料のことです。
元本を元に金額が決まり、完済するまで支払払います。
例えば1,000万円を7年で返済する場合、保険料総額は97,000円になります。

保険料は下記からシミュレーションできますの参考にしてください。
「特約料お支払額シミュレーション」
https://www.dansin.or.jp/insurance/business/simulation.php
この保険に入るか入らないかは自由だし、入らなかったからといって今後の融資が不利になることもありません。
自分の加入している他の保険の内容や迷惑をかけるかもしれない家族の状況、リスクに対する特約料の金額など、色々と考慮した上で、加入するかしないかを決断して下さい。
タグ :商工会議所
2022/01/17
さすがPayPayというか孫正義!と思った出来事がありました。
それは昨年10月1日から始まったPayPayの手数料ですが、実は「使用料」だったことに気づいたからです。
当商工会議所でもPayPayは導入していて、セミナー等々の参加費や利用料に使う方もいらっしゃいます。
先日、手数料(その時はそう思っていた)を確認したときです…
あれ?消費税ってなんだ?
うんと違和感を感じました。

というのも、クレジット決済の手数料は「非課税」のため消費税はかからないはずです。
詳しくは国税庁のサイトを参照

過ぎにPayPayの利用規約等々を見たところ、なんとPayPayは手数料ではなく「決済システム利用料」となっているではありませんか!
そしてご丁寧に「別税」と記載もあります。
つまり実質2.2%弱の利用料を払うということ。
そしてもっとめんどくさいのは、消費税の計算では「控除対象経費」となることです。
もー、手数料…もとい、利用料を安く見せるためこんな小細工つかうなってーの。

それは昨年10月1日から始まったPayPayの手数料ですが、実は「使用料」だったことに気づいたからです。
当商工会議所でもPayPayは導入していて、セミナー等々の参加費や利用料に使う方もいらっしゃいます。
先日、手数料(その時はそう思っていた)を確認したときです…
あれ?消費税ってなんだ?
うんと違和感を感じました。

というのも、クレジット決済の手数料は「非課税」のため消費税はかからないはずです。
詳しくは国税庁のサイトを参照

過ぎにPayPayの利用規約等々を見たところ、なんとPayPayは手数料ではなく「決済システム利用料」となっているではありませんか!
そしてご丁寧に「別税」と記載もあります。
つまり実質2.2%弱の利用料を払うということ。
そしてもっとめんどくさいのは、消費税の計算では「控除対象経費」となることです。
もー、手数料…もとい、利用料を安く見せるためこんな小細工つかうなってーの。

タグ :商工会議所
2022/01/15
何らかの経営課題を解決するため新しいアイディアを考えるとき、似たような業種業態の事業者さんが何をしているのか?を参考にするために調べたくなったり、実際に調べていると思います。
僕も事業計画の相談が来ると「同じようなことしている事業者さん居ないかなー」って調べます。
その調べる先はGoogle先生よりも、政府-経済産業省や中小企業庁が発行している「事例集」をまっさきに見ることが多いです。
この事例集は、全国の中小企業者さんが取り組む事業についてまとめられたもので、年に1回ぐらいかな…発行され商工会議所に届きます。
配布用もあるので欲しい方にはお配りしたりもしています。
この事例集、なかなかのもので参考となる事例がびっしり。
しかも、中小小規模企業の皆様の事例だからとっても参考となります。
そんな事例集が1年ほど前?から「ミラサポプラス」で公開、そして検索できるようになっています。
このデータベースには経済産業省が発行する色々な事例集が登録されているようで、ドンドン情報量が増えてきています。

「業種」「キーワード」「お悩みごと」等々色々なキーワード等々でも検索-絞り込みができるのでピンポイントで参考にしたい情報も検索できます。
一つ一つの内容も、わかりやすくそして大体5分もかからないうちに読めてしまう文字数です。
ヒント満載のこのデーターベース、ぜひご活用ください。(僕も当然活用しています)
僕も事業計画の相談が来ると「同じようなことしている事業者さん居ないかなー」って調べます。
その調べる先はGoogle先生よりも、政府-経済産業省や中小企業庁が発行している「事例集」をまっさきに見ることが多いです。
この事例集は、全国の中小企業者さんが取り組む事業についてまとめられたもので、年に1回ぐらいかな…発行され商工会議所に届きます。
配布用もあるので欲しい方にはお配りしたりもしています。
この事例集、なかなかのもので参考となる事例がびっしり。
しかも、中小小規模企業の皆様の事例だからとっても参考となります。
そんな事例集が1年ほど前?から「ミラサポプラス」で公開、そして検索できるようになっています。
このデータベースには経済産業省が発行する色々な事例集が登録されているようで、ドンドン情報量が増えてきています。

「業種」「キーワード」「お悩みごと」等々色々なキーワード等々でも検索-絞り込みができるのでピンポイントで参考にしたい情報も検索できます。
一つ一つの内容も、わかりやすくそして大体5分もかからないうちに読めてしまう文字数です。
ヒント満載のこのデーターベース、ぜひご活用ください。(僕も当然活用しています)
タグ :商工会議所
2022/01/14
現在、税務署は電子化をめちゃくちゃ推し進めています。
その一つがこれ『「年調ソフト」で電子化しましょう!』です。
そのチラシを見て勘違いする方が続出中です。

何を勘違いするのかって…
商工会議所に来るお客さまは「給与担当者」です。
そして、このソフトの正式名称は「年末調整控除申告書作成用ソフトウエアorアプリ」です。
つまりスタッフさん(従業員)が作る控除申告書の作成支援であって、それを基に給与担当者が行う源泉徴収票、総括表、報告書の作成ではありません。
源泉徴収票を効率よく作るためのデータをスタッフさん自らが作って、給与担当者を楽にしてあげるソフトウエアです。
ということを何度も何度も説明しています。
ということで、夫婦や数名のスタッフさんが多い商工会議所への相談事業者さんにはそれほど導入メリットがないかも…
(怒られるか?)
その一つがこれ『「年調ソフト」で電子化しましょう!』です。
そのチラシを見て勘違いする方が続出中です。
何を勘違いするのかって…
商工会議所に来るお客さまは「給与担当者」です。
そして、このソフトの正式名称は「年末調整控除申告書作成用ソフトウエアorアプリ」です。
つまりスタッフさん(従業員)が作る控除申告書の作成支援であって、それを基に給与担当者が行う源泉徴収票、総括表、報告書の作成ではありません。
源泉徴収票を効率よく作るためのデータをスタッフさん自らが作って、給与担当者を楽にしてあげるソフトウエアです。
ということを何度も何度も説明しています。
ということで、夫婦や数名のスタッフさんが多い商工会議所への相談事業者さんにはそれほど導入メリットがないかも…
(怒られるか?)
タグ :商工会議所
2021/12/20
今年もあと2週間となりました。
仕事の大晦日は3月ですが、アメフトでいう「第3クオーター」ということで振返りをしてみました。

今年4月から挑戦しているのが「専門家による個別支援」です。
全国の商工会議所、商工会では当たり前のようにやっていますが、当会議所ではずっと、ずーと避けていた支援方法です。
具体的には、専門家と商工会議所のスタッフが事業者さんの経営上の悩みを聞くことで、表面的な経営課題だけではなくその原因の源泉となっている箇所の気づきを得てほしいという目的の支援となります。
商工会議所的には「伴走支援」という言葉で表現されていて、今年は今までに十数者の皆様と対話をしてきました。
助けてくれる専門家の方々の対話力がうんと素晴らしく、支援を受けた多くの事業者産が支援の目的どおりの気づきをしてくれて、そのうち数社がすでに自走をし始めたり、その兆しがあったりします。
そしてもう一つ、こちらは挑戦というか事業者さんの声に僕が思う商工会議所の未来を創造させてくれたこの言葉です。
『自分の考えを他の人に見てもらって、その人の意見を聞くこと自分では考えもつかなかった、気が付かなかったことを知ることも分かるし、アイディアももらえるから、うんといいんだよね!」
それは現在開催している「第3期利益の組立図を作るゼミナール」に参加している事業者さん数名が僕や、参加していない事業者さんに伝えたことです。
このゼミナールでは、実際に作った事業計画をみんなで見合って、意見やアイディアを交換し合う「ワイワイガヤガヤワーク(通称:ワイガヤ)」があります。このワイガヤが新しい発見があると言ってくれる参加者が今年は多いんです。
しかも、参加していないお友達の事業者さんにも「これいいよー!めっちゃ発見あるよ!」って伝えてくれる方も。
確かに僕もそう思うんです。
ちょっと前のブログにも書きましたが、一人で悩んでいてもなかなか自分でもいいねーと思うアイディアは降りてきません。
10人入れば、10人の個性があるように、その見方も10種類あります。
ということはですよ…
上記に書いた「専門家による個別支援」にも専門家だけではなく誰かの個性が入ったらもっといいことが起こるんぢゃないか?と。
そんなコトをモンモンと思っていたときにハッと思ったのが「事業者さんどうしが支援しあえる仕組みができないか?」ということです。
なんと説明したらいいのか難しいですが、例えば「専門家の個別支援に他の事業者さんが同席して、意見交換をしてみる」とか、「事業者さんどおしが自分の思っていることを意見交換しあえる機会」とかどんなふうに実現したらいいのかはモヤモヤしていますが、商工会議所の新しいサービスとして提供できたらな…漠然と感じています。
…よく考えてみると、これって現実には結構あって、大きい所だと「長野県中小企業家同友会」とか、小さいところだと仲のいい経営者どうしの飲み会(無尽的に定期的に開催されているやつ)とかすでに仕組みかされています。
商工会議所らしい…ワイガヤでいいアイディア出ないでしょうか?
仕事の大晦日は3月ですが、アメフトでいう「第3クオーター」ということで振返りをしてみました。
今年4月から挑戦しているのが「専門家による個別支援」です。
全国の商工会議所、商工会では当たり前のようにやっていますが、当会議所ではずっと、ずーと避けていた支援方法です。
具体的には、専門家と商工会議所のスタッフが事業者さんの経営上の悩みを聞くことで、表面的な経営課題だけではなくその原因の源泉となっている箇所の気づきを得てほしいという目的の支援となります。
商工会議所的には「伴走支援」という言葉で表現されていて、今年は今までに十数者の皆様と対話をしてきました。
助けてくれる専門家の方々の対話力がうんと素晴らしく、支援を受けた多くの事業者産が支援の目的どおりの気づきをしてくれて、そのうち数社がすでに自走をし始めたり、その兆しがあったりします。
そしてもう一つ、こちらは挑戦というか事業者さんの声に僕が思う商工会議所の未来を創造させてくれたこの言葉です。
『自分の考えを他の人に見てもらって、その人の意見を聞くこと自分では考えもつかなかった、気が付かなかったことを知ることも分かるし、アイディアももらえるから、うんといいんだよね!」
それは現在開催している「第3期利益の組立図を作るゼミナール」に参加している事業者さん数名が僕や、参加していない事業者さんに伝えたことです。
このゼミナールでは、実際に作った事業計画をみんなで見合って、意見やアイディアを交換し合う「ワイワイガヤガヤワーク(通称:ワイガヤ)」があります。このワイガヤが新しい発見があると言ってくれる参加者が今年は多いんです。
しかも、参加していないお友達の事業者さんにも「これいいよー!めっちゃ発見あるよ!」って伝えてくれる方も。
確かに僕もそう思うんです。
ちょっと前のブログにも書きましたが、一人で悩んでいてもなかなか自分でもいいねーと思うアイディアは降りてきません。
10人入れば、10人の個性があるように、その見方も10種類あります。
2021/12/17一人でモンモンと考えるより、何人かでワイワイガヤガヤ相談すしたほうがナイスアイディアやヒラメキが降ってくることって多くの方が知っていると思います。でも僕の場合その「ワイワイガヤガヤ」を創るのがうんと難しい…あくまで僕の場合です。現在、仕事でとある案内パンフレットを作成しています。ただ、今まで…
ということはですよ…
上記に書いた「専門家による個別支援」にも専門家だけではなく誰かの個性が入ったらもっといいことが起こるんぢゃないか?と。
そんなコトをモンモンと思っていたときにハッと思ったのが「事業者さんどうしが支援しあえる仕組みができないか?」ということです。
なんと説明したらいいのか難しいですが、例えば「専門家の個別支援に他の事業者さんが同席して、意見交換をしてみる」とか、「事業者さんどおしが自分の思っていることを意見交換しあえる機会」とかどんなふうに実現したらいいのかはモヤモヤしていますが、商工会議所の新しいサービスとして提供できたらな…漠然と感じています。
…よく考えてみると、これって現実には結構あって、大きい所だと「長野県中小企業家同友会」とか、小さいところだと仲のいい経営者どうしの飲み会(無尽的に定期的に開催されているやつ)とかすでに仕組みかされています。
商工会議所らしい…ワイガヤでいいアイディア出ないでしょうか?
タグ :商工会議所
2021/12/13
記帳アプリがとてつもなく使いやすくなって、操作に慣れれさえすれば年を明けてすぐにやってくるあのおっっくな決算がうんと楽になります。
これは数年前より何人かの事業者さんを拝み倒し実験台になっていただいた結果全員が「変えてよかったー!」と言ってくれたことからも裏付けができます。
ただ「便利ですよ?試してみませんか?」とおすすめしてもなかなか導入しますと即決する方はいません。
その理由はたぶん自分にあっているかどうかわからない状態なので、新しいコトを覚える労力と、年に1万円弱かかる費用に対し「失敗したらすべてが無駄になるし…」とおう気持ちが働くからだと思います。

そんなコトを知ってか知らずか「やよいの青色申告」は無料で1年間の利用が出来るサービスがあります。
僕はコレを活用して「1年間無料ですよ、半年間ぐらいでダメだと思ったら辞めたらいいぢゃないですか。試してみませんか?」とおすすめしています。
ただお勧めするだけではなく、売上が自動に記帳されるairレジ等の無料レジサービスとセットでの導入を支援しています。
日々の売上を記帳するだけでも結構の労力です。
これが自動に出来るんだったら…
そして、この自動記帳のデモを用意しています。
あともう一つのデモ、それはスマホからの入力です。
スマホのアプリを立ち上げて記帳の簡単さを体験していただく。
この2つで多くの方が「やってみようか」と導入を考えてもらえます。
新しい方法を導入するんだったら来年早々がいいと思います。
僕も現在、新たに数名の方に「来年1月からやりましょうよー」ってお声がけをしています。
新しいコト、そしてお金がかかることなのでちょっと引けてしまいますが、来年の今頃は「よかったよー」って思っていただけると思いますので、ぜひご検討を。
詳しい内容はお近くの商工会議所、商工会でも教えてくれると思います。
これは数年前より何人かの事業者さんを拝み倒し実験台になっていただいた結果全員が「変えてよかったー!」と言ってくれたことからも裏付けができます。
ただ「便利ですよ?試してみませんか?」とおすすめしてもなかなか導入しますと即決する方はいません。
その理由はたぶん自分にあっているかどうかわからない状態なので、新しいコトを覚える労力と、年に1万円弱かかる費用に対し「失敗したらすべてが無駄になるし…」とおう気持ちが働くからだと思います。

そんなコトを知ってか知らずか「やよいの青色申告」は無料で1年間の利用が出来るサービスがあります。
僕はコレを活用して「1年間無料ですよ、半年間ぐらいでダメだと思ったら辞めたらいいぢゃないですか。試してみませんか?」とおすすめしています。
ただお勧めするだけではなく、売上が自動に記帳されるairレジ等の無料レジサービスとセットでの導入を支援しています。
日々の売上を記帳するだけでも結構の労力です。
これが自動に出来るんだったら…
そして、この自動記帳のデモを用意しています。
あともう一つのデモ、それはスマホからの入力です。
スマホのアプリを立ち上げて記帳の簡単さを体験していただく。
この2つで多くの方が「やってみようか」と導入を考えてもらえます。
新しい方法を導入するんだったら来年早々がいいと思います。
僕も現在、新たに数名の方に「来年1月からやりましょうよー」ってお声がけをしています。
新しいコト、そしてお金がかかることなのでちょっと引けてしまいますが、来年の今頃は「よかったよー」って思っていただけると思いますので、ぜひご検討を。
詳しい内容はお近くの商工会議所、商工会でも教えてくれると思います。
タグ :商工会議所